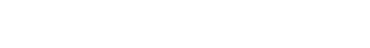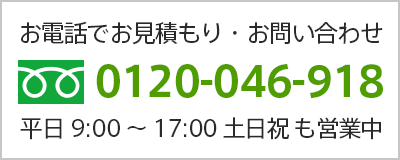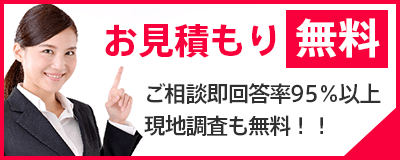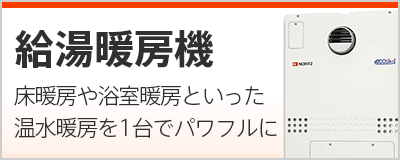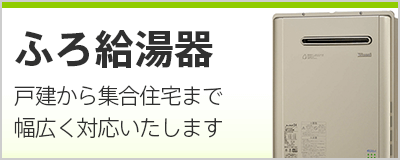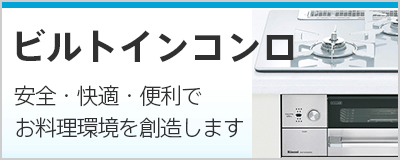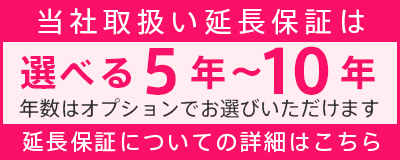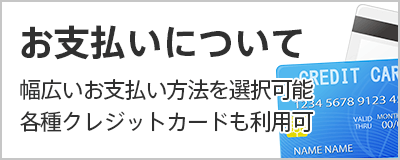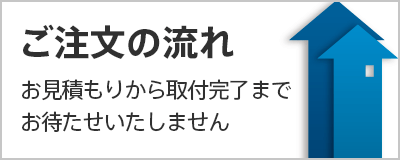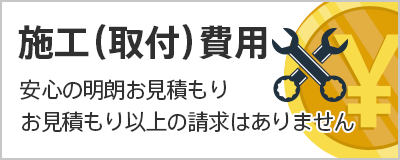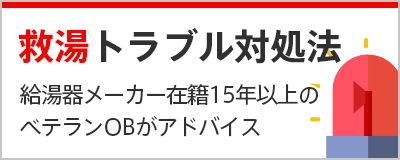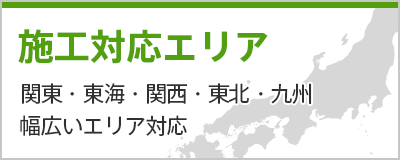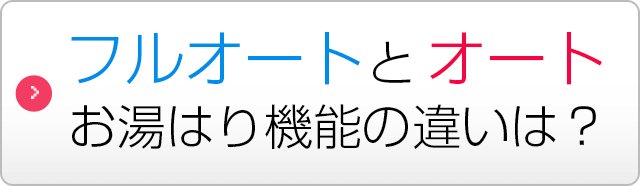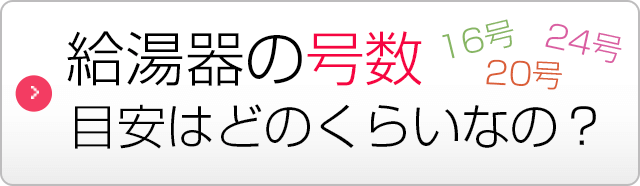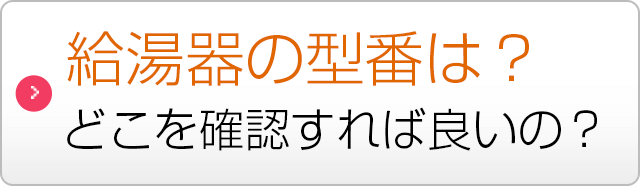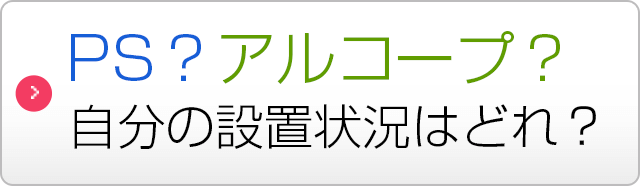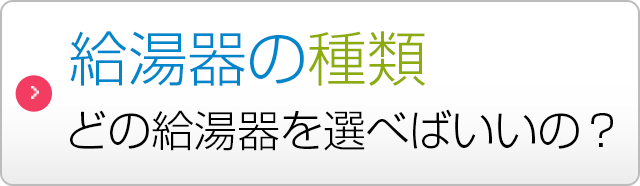No.151 次世代省エネ住宅設備機器の問題点は?
- 2011.07.05
震災後の節電要請から省エネ機器への関心がますます大きくなる昨今。
省エネ機器の購入を考えている消費者も当然これからも多くなるだろう。
■ただ、省エネ機器の普及等ともに気お付けなければならない、次世代省エネ機器の「効と罪」意外と見過ごす盲点。
今後飛躍的に普及するであろうと考えられる、われわれの関連の省エネ機器を考えてみた。
<燃料電池と太陽光ソーラー発電機器を例に考えてみた。>
●1)燃料電池
鳴り物入りで開発が進んでいるものの、まだまだ一般化には遠い機器。昨年から一部テスト的に販売は開始されているもののまだまだ一般化には時間がかかるし価格が高すぎる。
国の補助金頼りの機器。国の補助金が無ければ普及できない機器はまだまだ機器としては未熟と言わなければならないだろう。
①耐久年数が不安定。 メーカーが開発しテスト的に納入した機器のメンテ回数が多いと聞く現状は、まだまだ開発途中機器が一般家庭に認知されるまでには時間がかかる。
※確かに、技術はその積み重ねで進化すると言われるが?
②発電量が、コストに見合うのか?
一般的な開発機器は1KW程度の機器、一般家庭での消費電力3KWから4KW必要量には発電量は少ない。
<総合効率:発電と発熱(給湯利用)にて80%高率になると言われるも?>
本当にコストと見合う機器と言えるのか?開発までには時間もかかる。
③設置場所が限られる。機器の大きさは、電気給湯器「エコキュート」と同じ程度。
設置スペース的には、一般戸建家庭むけ。
将来的には有望機器であろうが、単独機器の次世代省エネ機器としては、当然まだまだ課題の多い機器。
太陽光発電との併用が最適と考えられるものの、セット購入となるとコストがバカ高くなる。
●2)太陽光発電
震災以降、福島原発事故に端を発した節電要請に伴い、一段と脚光を浴びてきた太陽光発電設備
確かに、自然エネルギーからの最大の贈り物。無尽蔵の資源。政府も大々的に普及に向けた取り組みを行うとのこと。<参入する企業も当然多くなる>
ただ、メリットばかり強調するもデメリットはあまり表面に現れない。
※当然デメリットもあると聞く。
①設備費が高く、耐久年数での償却はまず不可能に近いのが現状価格ではないのか?。
<価格が:4KWで100万円程度以下になるなら一般化するかも?>
※メーカーに耐久年数を聞くと、20年、25年とまちまち。
正確に聞くと、 公称「15年耐久」それ以後の耐久年数は、「期待年数?」
この「期待年数」とは「メーカーが、あと何年間は持ってほしいと期待する年数」・・・・?何だそのあやふやさは?
ということは実際何年耐久があるかは、わからないのが現状では?・・・メーカーの反論があるかな?
ただ、買う方は環境意識での取り付けに割り切るならそれもいいだろう。
②主力部品の、インバーターの耐久年数が今の段階では、ソーラーパネルの耐久年数内には一度は途中で交換が必要と聞く。ちなみに聞く話によれば7年程度? 短すぎるのでは?<開発余地が大きい>
③既築住宅に据え付けた時の、家本体メンテとの兼ね合いは?
家も、10年位に一度はメンテが必要。当然屋根部分の、メンテもある。
屋根改修時の、ソーラーパネルの撤去と再据え付け等の経費の可能性は?
<最近の新築の組み込み型のタイプならメンテも必要ないのかな?だが、後付けタイプ機器の場合は当然問題化するのでは?>
④ソーラーパネルに日の当るところと当たらないところがあると、部分的な影の影響でとソーラーパネルのセル耐久年数に影響があると聞くが?
■我々は素人的に聞く話に対して不安!
コストが非常に掛かる機器。買わせればいい!と言う。一時の商売道徳違反的なものにならないのか。
ある一定の、公平な情報を消費者に与えて公平な判断可能状態で普及に努めるのが最善では。
過去の事例に見られる「これはいいでしょ。絶対間違いない!と・・・・・・後になって:ごめんない。」
いつも泣くのは一般大衆。<笑うのは・・・一部の悪徳企業?と・・・関係者?>
現状住宅設備機器の耐久は、やはり10年から15年が一般常識<電子部品との兼ね合いが強い>
。その期間で、償却できる設備が最善と考えますが。いかがでしょうか。
※これはあくまで私的な考え方。情報が無いから不安が募る。<ぼやき>
※表があれば裏もある。今の政治状態じゃなんでもありなのか!・・・・寒いね時代が。
これじゃ、昭和の時代がまだましだった・・・かな?